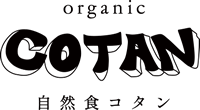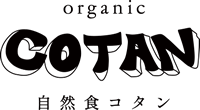昨日、コタンでの映画「チベットチベット」の上映に来てくれた皆さん、ありがとうございました。
あのスペースで、上映できるかなと思いながら当日の朝から準備をし、上映前に席は埋まり、立ち見の人が4,5人で上映開始。 思った以上のたくさんの人と映画を体験でき、上映後も、「ほかのいろんな人に見てもらいたいね。」という何人もの言葉が聞け、とても良い時間になったと思います。
ある体験をみなのなかで感じ、会話することで、その体験が特別で非日常的なものではなく、日常的な感覚に着陸するような気がしました。
今、個人の主義や趣味が進み肥大化することで、ある種の自由や繊細さが守られる一方、排他的な感情や不安感も成長し、自分と社会、自分と他人という境界線はますます濃くなっているでしょう。 多数で時間を共有すること、社会の風景としてではなくこういう人もいるんだと理解(許容)することは太い安心感を養ってくれていると感じました。
また、いい時間を作りましょう。 ありがとうございました。
あと、映画上映中に日常の買い物に来てくれていたお客さんも協力ありがとうございました。
コタンではイベントの時も、通常どうり全商品買い物できますので、気軽にお越しください。商品が探しにくい時はスタッフに声をかけてください。ご遠慮などなく。
~イベント告知~
今週 8月14日(木)の夜6時30分より コタン 岡大前店にて
海老原 よしえさん ライブコンサート あります。
アメリカインディアンの心のつながり、チベットの子供たちのサポートもしているよしえさん。
今回コタンでチベット映画を見て、新しい出会いを体験した人・・・そこからまたつながる夜になると思います。 うたと祈りの夜。 火をともします。 ぜひお越しください。
~海老原よしえ プロフィール~
シンガーソングライター。2002年に東京から長野に転居。長野県伊那市在住。
20代の5年間を海外で過ごし、特にアメリカインディアンの世界観を体感したことがその後の生き方に大きな影響を与える。長野に移って半年後、突然歌を歌いだす。
現在約100曲のオリジナル曲があり、その場のインスピレーションで歌を選び歌う。
FUJI ROCKやアースデイ東京、’広島原爆の火’が灯る福岡県 星の村の「広島デー平和式典」にも出演するなど活動範囲は幅広い。ライブの傍らチベットの子供たちのサポート、イラクへの医療支援、また女性の集い(内側の深いシェアリング)。2004年には富士での世界の民族による世界平和と祈りの日(WPPD)を開催。毎年夏の富士から九州までのツアーでは、そのツアーの収益の一部をイラク医療支援にあてている。
現在までにダラムサラ(北インド)のチベット子供村のサポートのためのベネフィットCDを含む自主製作のCDが3枚でている。